1976年(昭和51年)8月3日、日本の電子産業史における決定的な転換点となる製品が発売されました。日本電気(NEC)が送り出したマイクロコンピュータ・トレーニングキット**「TK-80」**です。この製品は、当初の目的であった産業用エンジニア向けの教育ツールという枠組みを遥かに超え、日本中に「マイコンブーム」を巻き起こす触媒となりました。
1. 誕生の背景:チップを売るための「教育」という戦略 当時、コンピュータといえば巨大なメインフレームを指し、個人が所有するなど夢のまた夢という時代でした。NECの半導体部門は、新たに開発したマイクロプロセッサ「μCOM-80」ファミリーを販売する必要に迫られていましたが、市場にはその「使い道」を知る者がほとんどいませんでした。
この窮地を救ったのが、後に「日本のパソコンの父」と呼ばれることになる渡邊和也氏です。米国視察で若者たちがコンピュータを個人の道具として楽しむ姿に衝撃を受けた渡邊氏は、「マイコンを売るためには、まず使い道を教えなければならない」と確信しました。
しかし、当時のNEC内には「コンピュータはコンピュータ部門が作るもの」という高い壁がありました。そこで渡邊氏らは、この製品を「完成品のコンピュータ」ではなく、あくまで部品を袋詰めした**「トレーニングキット(教育用教材)」**として定義することで、社内調整を回避したのです。
2. 技術的仕様:シンプルながら本質を突いた設計 TK-80のハードウェアは、マイクロプロセッサの動作原理を理解するための最小限の構成要素がワンボードに凝縮されていました。
• CPU: インテル8080Aと互換性のあるμPD8080Aを搭載(クロック周波数2.048MHz)。
• メモリ: ROMは768バイト、RAMは512バイトという極めて限定的な容量。
• インターフェース: 入力には16進キーボード、表示には8桁の7セグメントLEDを備え、高価な外部端末を必要としませんでした。
プログラミングは、紙に書いたアセンブリ言語を手作業で16進コードに変換する**「ハンドアセンブル」**という原始的な手法で行われました。ユーザーはキーボードを叩いてコードをメモリに打ち込み、CPUがそれを実行してLEDが光る様子を見ることで、コンピュータの仕組みを身体的に理解していきました。
3. 社会現象としての「マイコンブーム」と聖地の誕生 TK-80は、発売後2年間で約6万6,000台、シリーズ累計で7万台以上という、当時の常識を覆す大ヒットを記録しました。88,500円という価格は当時の大卒初任給に匹敵する高額でしたが、エンジニアだけでなく、中高生までもが夢中になりました。
この熱狂を支えたのが、秋葉原のラジオ会館に開設されたサービスセンター**「Bit-INN(ビットイン)」**です。ここは単なるサポート拠点ではなく、技術者や少年たちが情報を交換し、自作のプログラムを自慢し合うコミュニティの場となりました。また、この時期に創刊された『月刊I/O』や『月刊アスキー』といった専門誌も、TK-80の普及を強力に後押ししました。
さらに、TK-80は技術情報の公開を積極的に行う**「オープン方式」**を採用していました。この設計思想のルーツは、渡邊氏らが学んだ米DEC社のミニコン「PDP-8」にあります。回路図や基本ソフト(モニタ)のプログラムリストを公開したことは、当時の企業文化としては画期的なことでした。
4. 拡張と進化:PC-8001への道 ユーザーの要求が高度化するにつれ、NECは機能拡張ボード**「TK-80BS」**を発売しました。これにより、BASIC言語の使用や、家庭用テレビをディスプレイとして利用することが可能になり、マイコンはより「パソコン」に近い形態へと進化しました。
TK-80で培われた技術的知見とユーザーコミュニティは、1979年発売の**「PC-8001」**へと結実します。PC-8001の開発コードネームは存在せず、当初はそのまま「PC-8001」と伝票に書かれていたという逸話も、当時の勢いを物語っています。
5. 現代に続くレガシー TK-80は2010年、情報処理学会によって**「情報処理技術遺産」**に認定されました。また、その魅力は現代でも色褪せず、シミュレータやエミュレータ、あるいは「ZK-80」といった互換キットを通じて、今なお多くの愛好家に親しまれています。
TK-80が残した最大の遺産は、ハードウェアそのものよりも、**「コンピュータを個人の手に開放した」**という意識の変革にあります。1970年代の秋葉原でハンダ付けに没頭した少年たちが、後の日本のIT・ゲーム産業を支える技術者へと育っていったのです。



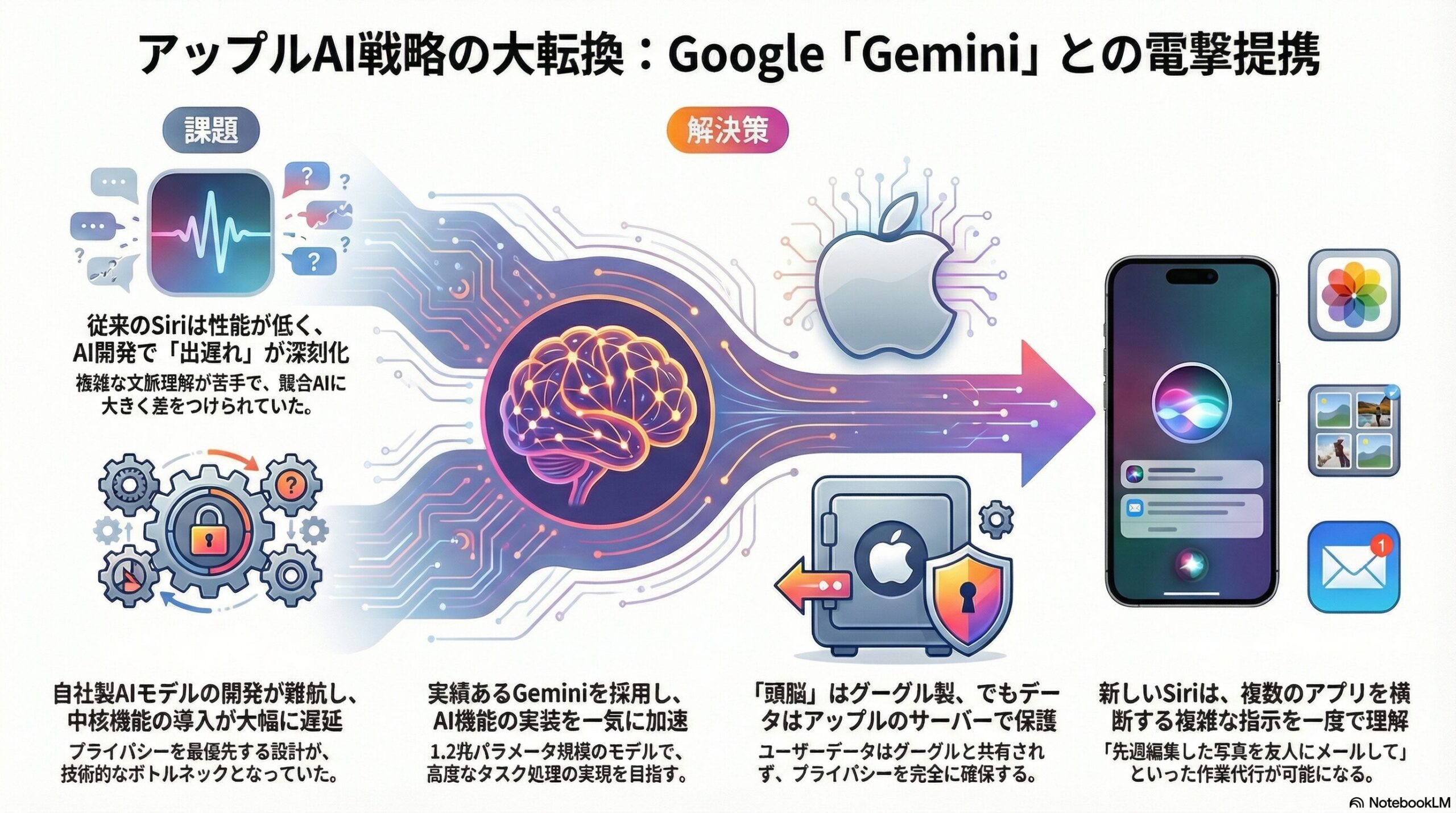

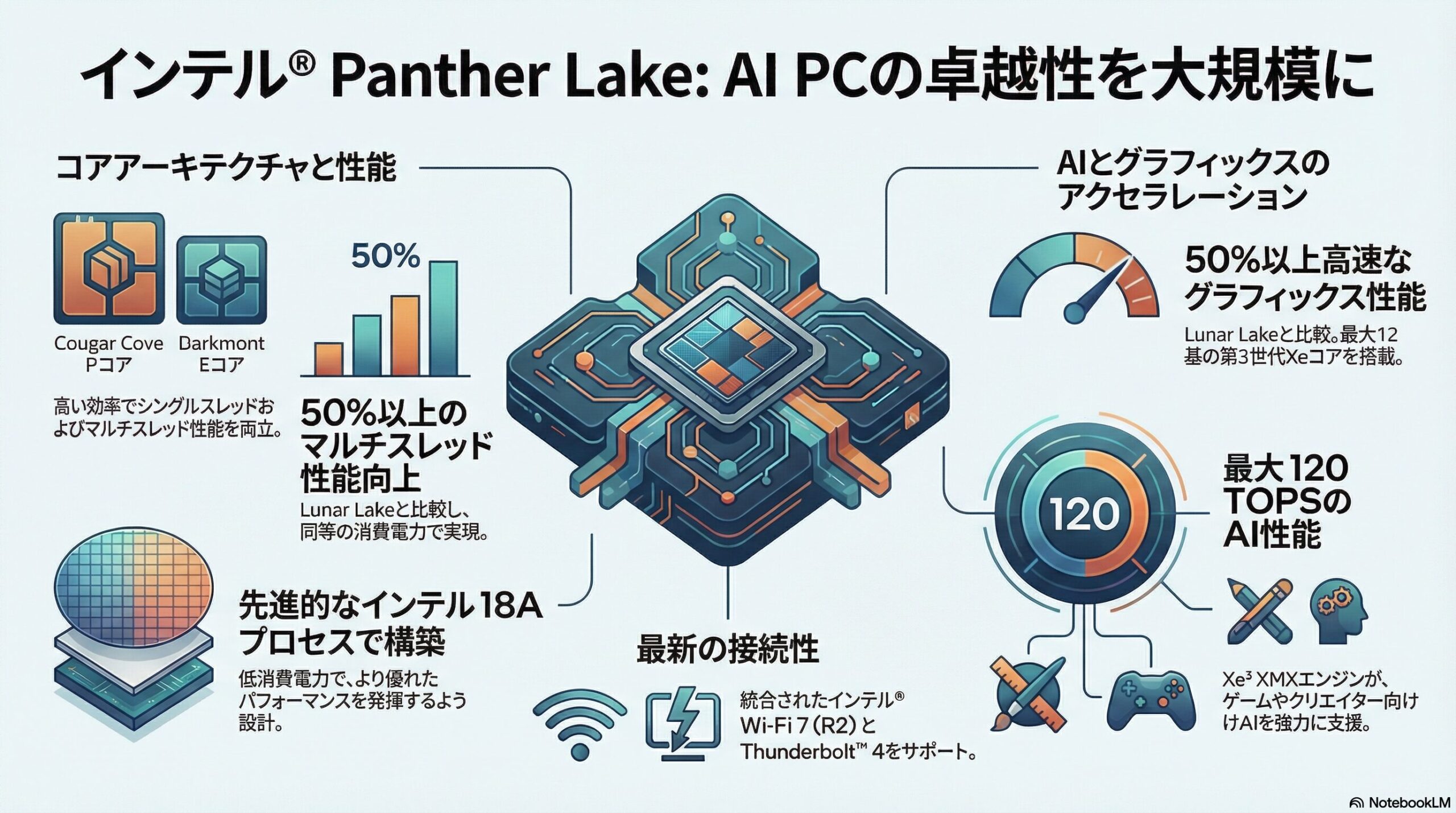
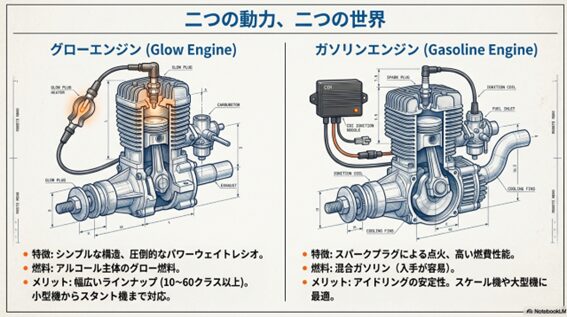

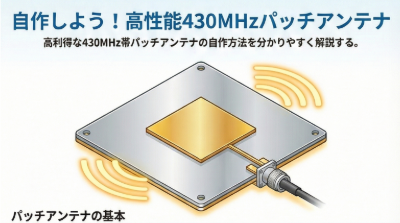

コメント